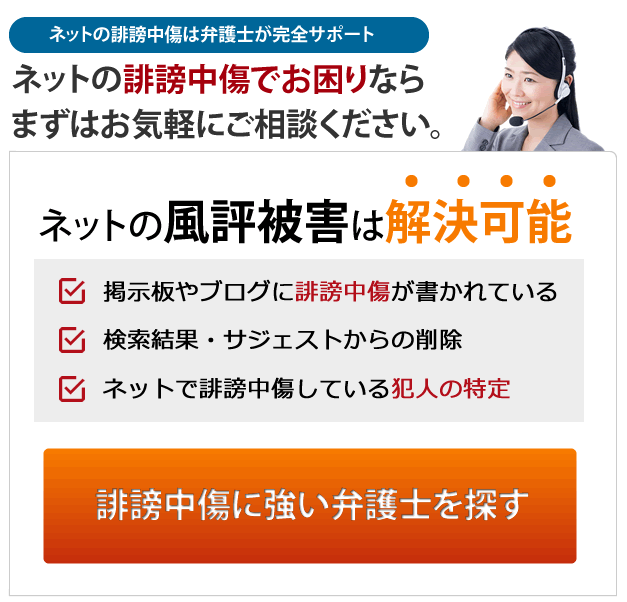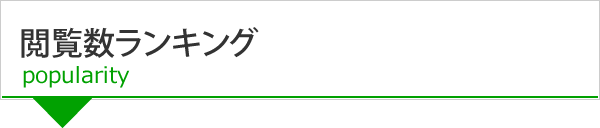誹謗中傷サイトが削除されたら検索結果の削除とキャッシュ削除と更新!

特定の個人や企業を誹謗中傷する内容の書き込みは、削除してもらってそれで終わりではありません。検索エンジンにまだその内容が残っているからです。そのため、Googleなどの検索エンジンを運営する企業に対して、検索結果の削除とキャッシュやスニペットの更新をしてもらう必要があります。その方法についてみていきましょう。
誹謗中傷はコンテンツの削除だけでは終わらない
あるサイトに自分のことを誹謗中傷する内容が書き込まれたとき、そこの管理人に削除依頼をして無事に削除がされても、それで安心できるわけでありません。誹謗中傷の内容が削除されたとしても、しばらくは検索画面にその内容が表示され続けるからです。
コンテンツ削除の次にすべきこととは
まず、サイト管理人に誹謗中傷の内容を含むコンテンツやサイト自体を削除するよう要請します。それらの内容が削除されたのを見届けたのちに、今度はGoogleなどの検索エンジン側にキャッシュの更新や検索結果からの削除をただちに行ってもらう必要があります。
検索結果から削除する
誹謗中傷の内容を含むサイト自体を削除すると、そのサイトはもう存在しなくなるため、検索エンジンのデータベースからも削除してもらうよう、検索エンジンの運営元に依頼しましょう。
キャッシュとスニペットの更新
キャッシュとは、検索エンジン上で一時的に保存されているデータのことです。また、スニペットとはページタイトルの下に出てくるディスクリプション(説明文)のことです。サイトの中の誹謗中傷を含む部分のみを削除したときは、これらを更新してもらう必要があります。
検索結果の削除やキャッシュなどの更新が必要な理由
では、なぜ元のサイトそのものを削除したり、内容を変更すると検索エンジンの検索結果を削除したりキャッシュやスニペットの更新をする必要があるのでしょうか。その理由は、Googleの検索システムの特徴にあります。
検索結果から特定のサイトにたどり着くケースが多い
あるキーワードについて知りたいとき、多くの人は検索エンジンを利用して知識を得ようとします。そのとき、タイトルやスニペットに特定の誰かを誹謗中傷するような内容が出てくると、多くの場合そこに目が行きがちです。一説によると、ネガティブワードが人を引きつける力は、ポジティブワードの3倍とも言われています。
キャッシュやスニペットが更新されるのは数日〜数ヶ月に1回
実は私たちの知らないところで、GoogleクローラーとよばれるGoogleが開発した自動巡回プログラムが毎日世界中に公開されているサイトを巡回しています。Googleクローラーがあるサイトにやって来るのは数日~数か月に1回であり、それまでキャッシュやスニペットは更新されないため、強制的に更新する必要があるのです。
Googleの検索結果に出ないようにするためには
Googleの検索結果に誹謗中傷の内容が出てこないようにするためには、まずGoogleにデータベースの削除や更新のリクエストをします。それに対応してもらえないようであれば、ネット問題に強い弁護士に対処を委ねる方法もあります。
 検索エンジンとは?ちょっと踏み込んで考えてみよう
検索エンジンとは?ちょっと踏み込んで考えてみよう
Googleに削除をリクエストする
まずは、自力でGoogleに古いキャッシュやスニペットの削除のリクエストを出してみましょう。Google側に問題なく承認されれば、すみやかに対処してもらえます。具体的な手順は以下のとおりです。
Googleのアカウントを取得
はじめに、Googleのアカウントを取得します。このアカウントがなければ削除の手続きができるページにたどり着くことができない仕様になっているためです。「Google検索結果削除リクエストツール」のページにアクセスし、取得したアカウントのパスワードを入れてログインすると、削除依頼をするページに入ることができます。
「古いコンテンツの削除」で依頼
「URLの例」と書かれた窓に削除してほしいURLを入力し、「削除をリクエスト」と書かれた赤いボタンを押下します。しかし、削除をリクエストしても100%削除してもらえるわけではないので注意が必要です。
弁護士に削除依頼を委託するのもひとつの方法
もしGoogle側が削除リクエストに応じない場合は、ネット問題に強い弁護士に相談して削除への対応を依頼しましょう。その際、GoogleやYahoo!などの検索エンジンへの対応実績が豊富な弁護士に依頼すると安心です。
Googleとの任意交渉を行う
弁護士に依頼をすると、まずGoogleに対して任意の交渉で検索結果の削除を求めます。任意での削除が難しいようなら、裁判所に仮処分の申立てを行う、もしくは訴訟を提起する方法もあります。
米国のGoogle本社を相手取っての仮処分・裁判になることも
訴訟を起こすときは、Googleの日本法人ではなく、米国の本社を被告として争うことになります。かつては外国法人を相手取っての訴訟は困難でしたが、近年FacebookやTwitterなどの海外に本社を持つ企業を相手方とする訴訟が増加しており、ネット問題を扱う弁護士たちはそのノウハウを蓄積してきています。
ついに裁判所がGoogleに検索結果削除の仮処分命令を下した!
平成26年10月9日、東京地方裁判所が米国のGoogle本社に対して検索結果の削除を命じる仮処分決定を下しました。このことは非常に画期的なニュースであり、海外メディアでも大きな話題となりました。
過去の事例では「検索結果に非はない」とされていた
これまでも、GoogleやYahoo!などの検索エンジンに対する検索結果の削除を求めて何度も争われてきましたが、その度に原告が敗訴する結果に終わっていました。その理油とは一体何だったのでしょうか。
「検索結果はGoogleの意思を示したものではない」
従来、裁判所は「検索画面は検索した結果を表示しているだけであり、被告(Google)自身の意思を示しているわけではない」とのスタンスをとっていました。その理由としては、Google側の「検索エンジンは機械的に情報を収集しているだけであり、内容については感知しない」との主張に引っ張られていたことがあげられます。
「一部抜粋された内容が表示されても不法行為ではない」
また、「Aは犯罪者だ」など特定の誰かを誹謗中傷する内容が検索結果として表示されることがあっても、従来の判例では「表示される分量や検索エンジンの利用者の受け取り方などを考慮すると、不法行為を成立するとまでは言えない」と考えられていました。
東京地裁が検索結果についての明確な人権侵害を認める
しかし、今回の東京地裁の決定では、たとえ検索エンジンの検索結果に誹謗中傷する内容を表示しただけでも不法行為が成立することを裁判所が認めたことになります。裁判所が従来の論調を覆す決定をしたとのことで、マスコミ各社にも大きく取り上げられる事態となりました。
検索結果やスニペットが人格権の侵害にあたる
東京地裁はまず、今日インターネットで効率的に調べ物をするときに検索エンジンが重要な役割を果たしていることが「公知の事実である」ことに触れています。その上で、東京地裁は「記事の個々のタイトル及びスニペットそれ自体から債権者の人格権を侵害しているが認められる」と述べました。
 googleサジェスト裁判|日本でも差し止めと慰謝料の支払い判決に
googleサジェスト裁判|日本でも差し止めと慰謝料の支払い判決に
EUの「忘れられる権利」判決が影響も
今回の東京地裁の決定が従来の判決内容を覆すに至ったのは、同年5月にEU司法裁判所が「忘れられる権利」を認める判決を下したことが影響していると言われています。この判決では、Googleも他のサイト管理者と同様に違法な情報を削除しなければならない役割があるのは当然として、Googleに違法な情報に関する検索結果の削除を求めました。東京地裁の判決もこの考え方を踏襲して、Googleに削除義務を負わせる仮処分決定をしたのです。
 「忘れられる権利」で逮捕歴や過去の過ちの削除を求める
「忘れられる権利」で逮捕歴や過去の過ちの削除を求める
サイトや書き込みそのものを削除しても検索画面にはしばらくその内容が残り、引き続き多くの人の目に触れてしまいます。インターネットで誹謗中傷されて困ったときには、ネット問題に強い弁護士に削除を依頼するとともに検索結果の削除やキャッシュやスニペットの更新などの「後処理」まできっちりしてもらうようにしましょう。